人生の旅の途中、私たちは道に迷わないように羅針盤を使います。保険という旅の備えも、漠然と加入するのではなく、羅針盤のように賢く使うことが大切です。
今回は、あなたが保険で「損をしない」ための3つの羅針盤をご紹介します。
羅針盤1:死亡保障の「ゴール」を決める
「もしも」の時、遺された家族が困らないようにするための死亡保険。では、具体的にいくらの備えがあれば安心なのでしょうか?
ここで大切なのは、**「必要な保障額=残された家族の必要額 − 遺された家族が受け取れるお金」**というゴールを決めることです。
例えば、40代のAさん一家を想像してみましょう。 夫(40歳・会社員)、妻(40歳・専業主婦)、子ども2人(10歳と7歳)。
もし夫に万が一のことがあった場合、残された家族が困らないためには、いくら必要になるかを計算します。
- 遺された家族の必要額
- 生活費: 子どもが独立するまで、仮に20年間、毎月20万円の生活費が必要だとすると、20年×12ヶ月×20万円=約4,800万円です。
- 教育費: 大学卒業までの教育費を子ども1人あたり1,000万円とすると、2人分で約2,000万円です。
- 住居費: 住宅ローンが残っている場合、残債を考慮する必要があります。仮に約2,000万円としましょう。
- その他: 葬儀費用や非常時の予備費として約500万円と見込みます。
- 合計:約9,300万円
- 遺された家族が受け取れるお金
- 遺族年金: 遺族年金のうち、公的制度である遺族基礎年金は「子どもが18歳になる年度末まで」支給されます。今回は下のお子さんが7歳なので、あと11年間(18歳ー7歳)受け取ることができます。遺族基礎年金と遺族厚生年金の合計で、年間約150万円を受け取れるとすると、11年 × 150万円=1,650万円となります。
- 死亡退職金: 勤務先の規定に応じて受け取れるお金です。約500万円としましょう。
- 貯蓄: これまでに準備してきた貯金が約500万円あるとします。
- 合計:約2,650万円
- 必要な保障額
- 必要額(約9,300万円)から、受け取れるお金(約2,650万円)を引くと、約6,650万円の保障が必要という計算になります。
このように、必要な金額を具体的に計算することで、過剰な保障を避け、無駄な保険料を払うことがなくなります。
羅針盤2:医療保険の「自己負担額」を知る
病気やケガで入院した時、どのくらいの医療費がかかるかご存知ですか?
日本の公的医療保険には**「高額療養費制度」**があり、1ヶ月の医療費の自己負担額には上限が設けられています。
例えば、年収500万円の会社員が医療費100万円の手術を受けたとしても、自己負担額は80,100円+(100万円-267,000円)×1%=約8万7,000円程度で済みます。
しかし、この制度でカバーされない費用もあります。
- 差額ベッド代: 全国平均で1日約6,000円かかり、入院が長引くと大きな負担になります。
- 食事代: 1食あたり約460円の自己負担があります。
- 先進医療費: 公的医療保険の対象外で、数百万円かかる治療もあります。
これらの自己負担額をどのくらいまで許容できるかによって、必要な医療保険の保障内容や金額が変わってきます。「差額ベッド代は払えるから、先進医療特約だけは付けておこう」といったように、必要な保障を賢く選ぶことが大切です。
羅針盤3:貯蓄型より「運用」で資産を育てる
「保険で貯蓄もできるから便利」と考える方も多いでしょう。しかし、貯蓄型保険は解約返戻金や満期金がある一方で、資産を増やすという点では効率が悪いのが一般的です。
- 貯蓄型保険の利回り:年利0.5%程度
- つみたてNISAやiDeCoの運用:年平均3〜5%程度(元本割れするリスクもあります)
老後資金など、長い時間をかけて準備するお金は、保険の貯蓄機能に頼るのではなく、つみたてNISAやiDeCoといった運用制度を賢く活用する方が、効率的に資産を増やすことができます。しかし、運用しだいでは元本割れのリスクがあるため、損をしない受取に向けた出口戦略が必要になります。
まとめ:自分だけの「羅針盤」を手にしよう
保険選びに「正解」はありません。しかし、「羅針盤」を持つことで、あなたにとって最適な道を見つけることができます。
- 死亡保障は、必要額を具体的に計算する。
- 医療保険は、公的制度を理解した上で自己負担額に備える。
- 長期的なお金は、貯蓄型保険ではなく運用で増やす。
この3つのポイントを意識して、あなただけの「保険の羅針盤」を手に入れてください。具体的な保障額の計算について、さらに詳しく知りたい場合は、ぜひファイナンシャルプランナーにご相談ください。


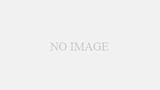
コメント