人生の旅の途中で、もし自分に万が一のことがあったら、遺された家族はどうなるんだろう…? 特に40代は、子育てや住宅ローンなど、家計を支える責任が重くなる時期です。 「今の備えで、家族は困らないだろうか?」 「そもそも、いつまで備えればいいんだろう?」
こうした不安は、誰しもが抱えるものです。死亡保険は、大切な家族に「安心」という名のバトンを渡すための、最も重要な旅の道具の一つです。この記事を読んで、漠然とした不安を解消し、ご家族を守るための賢い備え方を知ってください。
この記事を読んで解決できること
- 死亡保険が「いくら」必要なのか、具体的な金額の目安がわかる
- 公的保障を前提にした、賢い死亡保険の選び方がわかる
- 遺族年金の受給期間など、知っておくべき公的制度のポイントがわかる
- 40代夫婦を例にした、保険料の具体的なイメージがわかる
必要な保障額は「いくら」?〜ゆとりある生活を送るための目安〜
生命保険文化センターの調査(令和元年度)によると、一家の働き手に万が一のことがあった場合、遺族が最低限の生活を営むために必要な年間生活費は209.7万円、ゆとりある生活を送るためには360万円とされています。
この調査結果を参考に、40代夫婦(妻は専業主婦、子ども2人)が、子どもが独立するまでの期間に「ゆとりある生活」を送るための必要保障額を考えてみましょう。
子どもの独立まで
仮に、あと20年間、月30万円の生活費が必要だとすると、7,200万円が必要です。(30万円 × 12ヶ月 × 20年) この金額から、遺族年金などの公的保障や貯蓄を差し引いて、足りない分を死亡保険で補います。
公的保障の活用
族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金から成り、子どもの年齢によって受給額と期間が変わります。特に、遺族基礎年金は子どもが18歳になる年度末までの支給です。公的年金の受給額は年収や加入期間で変わりますが、月10万円〜15万円程度を想定しておくとよいでしょう。 例えば、遺族年金で月15万円を受け取れる場合、**「足りない月15万円を保険で補う」**という考え方が賢い選び方です。
賢く選ぶための「旅の道具」図鑑
死亡保険には様々な種類がありますが、主なものに絞って見ていきましょう。また、40代夫婦(夫40歳・会社員)が、万が一に備える場合の、それぞれの保険料の目安も確認してみてください。
収入保障保険(月15万円を20年間)
もしものことがあった場合、遺された家族が自立するまで、毎月決まった金額を年金形式で受け取れる保険です。保険金額は時間の経過とともに減っていきますが、その分保険料が安く設定されています。**前項で挙げた「足りない月15万円を補う」**という考え方に最も適した保険と言えるでしょう。
保険料の目安は、月々3,000円〜5,000円程度 。保険料を抑えつつ、必要な保障を確保したい場合に適しています。
終身保険(保障額500万円)
保障が一生涯続く保険です。もしもの備えと、将来に向けた貯蓄を両立させたい場合に向いています。解約返戻金が貯まっていくため、老後資金としても活用できますが、その分保険料は高めです。
保険料の目安は、月々10,000円〜15,000円程度 。保障と貯蓄を兼ねたい場合に適しています。保障額を増やすと、保険料はさらに上がります。
定期保険(保障額3,000万円を20年間)
一定期間だけ保障を得る保険です。最も保険料が安く、子育て期間や住宅ローンを返済する期間など、特定の時期に大きな保障を安価に確保したい場合に適しています。
保険料の目安は、月々3,000円〜6,000円程度 。大きな保障を一定期間だけ確保したい場合に適しています。
まとめ:さあ、大切な家族のために、今こそ「命のバトン」を準備しよう
死亡保険は、単なる金融商品ではありません。あなたが愛する家族に、経済的な安心という名のバトンを渡すための、大切なメッセージです。
この機会に、ご家族と「もしも」について話し合い、あなたにぴったりの「命のバトン」を見つけてください。


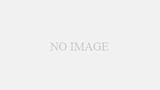
コメント